これからサウナデビューする人、最近サウナデビューした人、サウナのことが気になっている人、”ととのう”って何なの?!という人へ…
まずはここから。
この記事を読めば、サウナに行くのに知っておきたいことがひととおり分かります!
- サウナの楽しみ方をサクっと知りたい
- 知っておくと良いことをひととおり網羅したい
- 何から見ていいか分からないからとりあえずまとめて!
サウナの基礎知識

まずは、サウナの基礎知識からサラっと見ていきましょう。
サウナの種類
サウナは「ドライサウナ」と「ミストサウナ」の2つに分けられます。
大きく違うのは、温度と湿度です。
- 乾式サウナ(ドライサウナ)…温度は高く(70℃前後~100℃前後)、湿度は低い
- 湿式サウナ(ミスト/スチームサウナ)…温度は低く(40℃前後~60℃前後)、湿度は高い
「サウナ」と言われて木のベンチや壁に囲まれた空間をイメージしたならば、それは乾式サウナ。
室内はサウナストーブにより温められ、カラッとしているのが特徴です。
対して、湿式サウナは、タイル張りの空間であることが多く、空間中に蒸気が充満しているようなサウナです。
湿式サウナの中には、室内にマッサージ用の塩やパック用の泥が置かれ「塩サウナ」や「泥サウナ」として楽しめるサウナもあり、女性人気も高いです。
サウナ室の温度
乾式サウナの室内は階段状になっていることが多いです。
この場合、同じサウナ室内でも座る位置により温度が大きく変わります。
空気は温められると上部に溜まる性質があり、サウナ室内は、上段ベンチに行くほど熱くなっています。
ベンチ1段分で、約10℃の温度差がある場合も。
そのため、座る位置を変えることによって、ある程度は熱さをコントロールすることができます。
もっと詳しく知りたい人は、是非こちらの記事も読んでみてください。↓
サウナの効果
サウナに入ると、様々な効果を得られます。
とにかく、いいことづくめなんです!
- 疲労回復
- ストレス解消
- 活力や気力不足の解消
- 安眠効果
- 美肌づくり
- 落汗減量(汗を出し切る)
(参考:公益社団法人日本サウナ・スパ協会HP内『サウナ読本』、サウナ・スパ健康アドバイザー公式テキスト)

いわゆる”ととのう”入り方は、自律神経を整えてくれる効果があるので、私はいつも、心が穏やか&ポジティブになっていくのを強く感じます!
サウナで”ととのう”
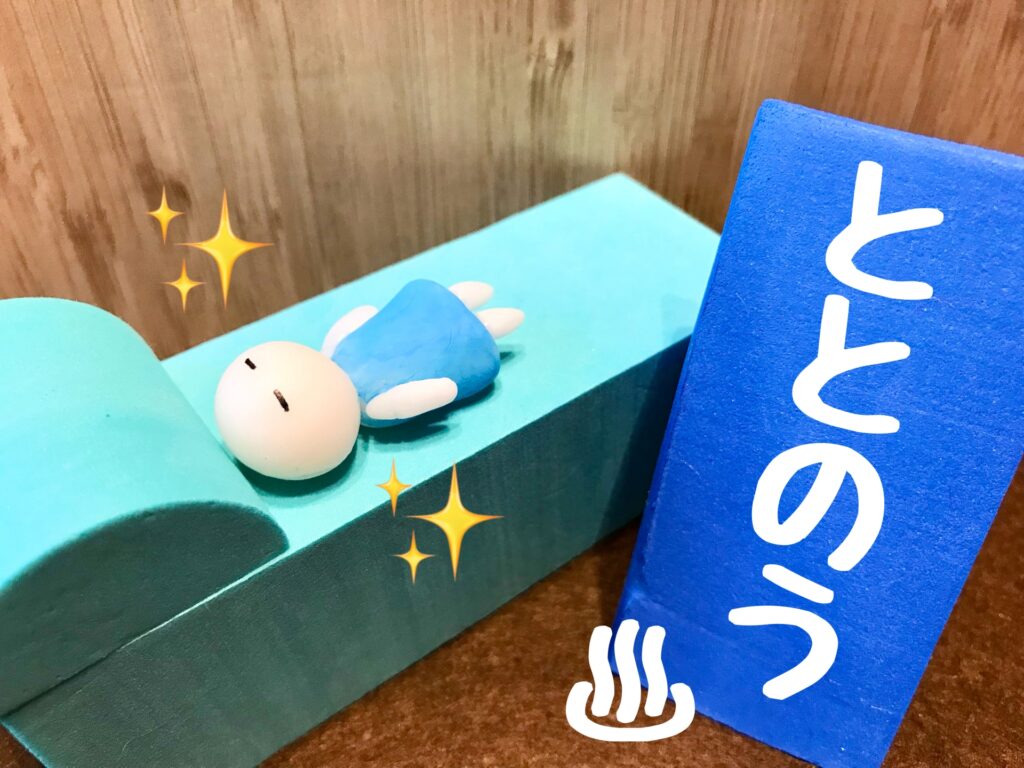
サウナといえば”ととのう”!というくらいに、よく耳にするようになったこの言葉。
ととのう感覚を味わってみたい!と、サウナに興味を持った人やこのページにたどり着いた人も多いのでは?
“ととのう”とは
“ととのう”とは、サウナ→水風呂→休憩(外気浴)を2~4セット繰り返す中で休憩中に感じる、この上ない恍惚感・ディープリラックス状態のことです。
サウナの熱さ→水風呂の寒さという、身体にとっては危機的な状況の連続から一気に解放され、副交感神経が優位になることでやってくるとされています。
ととのう感覚は、こんな風に表現されることもあります。
- 多幸感でいっぱいになる
- 頭の中がクリアになる
- 身体がすっきりして軽くなる
- 悩み事や心配事に対してポジティブになる
- 全身の感覚が敏感になる→風や空気の心地よさを感じる
- 味覚が敏感になる→ご飯が何倍も美味しく感じる(サウナ飯)

多くのサウナーたちは、この、ととのう感覚にとりつかれ今日もサウナに通っています。そう、私も。(笑)
「ととのう」についてもっと詳しく知りたい人はこちらをチェック↓
“ととのう”基本の入り方
基本の入り方はこちら。
事前に十分な水分補給をしておくことと、サウナ室に入る前に全身の汗を流すのをお忘れなく。
また、サウナ浴・外気浴の前には身体についた水分を1滴残らず綺麗に拭き取るのもポイントです。

身体についた水分は蒸発するときに体温を奪いますからね!
もっと詳しく…!という人はこちらの記事をチェック↓
サウナの持ち物
サウナに行くとき持っていきたいものはこちら。
注目していただきたいのはこちらです。↓
- サウナで頭に巻くタオルorサウナハット※長めのフェイスタオルがおすすめ
→サウナをじっくり楽しみたいならのぼせ防止・髪や頭皮の保護のために必須! - 飲み物(500ml~1000ml以上)
→サウナ1セットあたり300~400mlの汗をかく!安全に楽しむために必須!

サウナを楽しみに温浴施設に行くなら最低限これらはお忘れなく!
サウナを楽しみに温浴施設に行くなら最低限これらはお忘れなく!
持ち物についてもっと詳しく紹介している記事はこちら↓
サウナのマナー
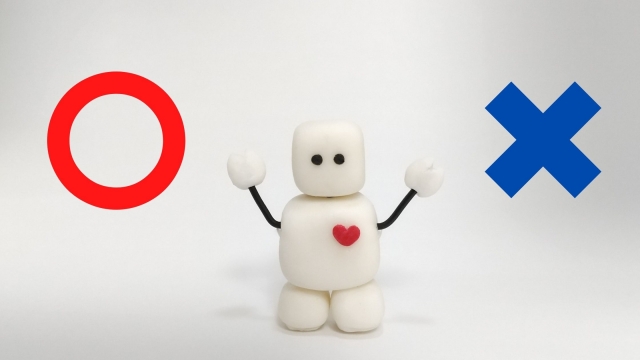
サウナにはマナーがあります。
他のサウナーさんたちとも思いやりあってサウナを楽しめるように、是非知っておきたいサウナのマナーを12つご紹介します。
- サウナ前に身体を洗う
- 身体と髪の水滴を拭き取ってサウナに入る
- サウナ室内に飲み物を持ち込まない
- サウナ室内でタオルを絞らない
- 黙サウナ
- サウナ室内や休憩スペースの場所とりをしない
- 共有サウナマットを持ち歩かない
- 水風呂に入る前に汗を流す
- 水風呂に潜らない
- 水風呂には静かに入水する
- 休憩後はチェアを洗い流す
- ととのえ中に話しかけない
これらをおさえておけば安心、初心者でも優良サウナーとして胸を張ってサウナに入ることができます!
12つの項目についてはこちらの記事で詳細に解説しています↓
サウナハットについて

サウナハットとは、サウナ室内でかぶるこんな帽子です。
どこかで見たことがあるのではないでしょうか?
サウナハットの効果
サウナハットは、ただのファッションアイテムではありません。
サウナを安全に最大限楽しむために是非持っておきたいアイテムなんです。
- 頭部を熱から守りのぼせを防止する
→サウナではより上にある頭部が身体より先に熱くなり、身体が芯まで温まる前にのぼせてしまうことも! - 髪や頭皮を保護する
→濡れた状態の髪はダメージを受けやすい!抜け毛につながることも!
そのほか、サウナ室での使用の快適性をさらに考えられたハットもあります。
- 大き目サイズ:深くかぶることで熱波から鼻や口を守れる
- ポケット付き:耳栓や熱くなりがちなロッカーキーをしまえる
嬉しいメリットですね!
タオルで代用することもできますが、効果の高さの違いや快適性のメリットから考えて、サウナハットを持っておくのが圧倒的におすすめです。

初めはタオルで代用して、よく行くようになったらサウナハットの購入を考えるのがいいでしょう!
ちなみに、タオルで代用する場合は、鼻や口も同時に守れる『忍者巻き』という巻き方があります。
サウナハットの種類
サウナハットには色々な素材で作られたものがあります。
素材が異なるとそれぞれメリットも違うので、複数持ち使い分けるサウナーも多いです。
- 羊毛(ウール)…断熱効果が高い。汚れが付きにくい。
- 綿、タオル地…洗濯機洗いができお手入れが簡単なものが多い。
- 化学繊維…高機能素材が使用され断熱効果の高さとデザイン性を兼ね備えたものも多い。
どんなものがあるのか見てみたい人は、こちらも是非チェックしてみてください。↓
最新のおすすめサウナハット情報をまとめています。
サウナ用語
サウナ用語は非常にたくさんあります。
その中からまずはこれだけは知っておきたい!というサウナ用語をご紹介。
ととのう
サウナ→水風呂→休憩(外気浴)を2~4セット繰り返した際に休憩中におとずれる、恍惚感・ディープリラックス状態のこと。
ロウリュ
サウナストーブの上のサウナストーンに水をかけて蒸気を発生させること。
ロウリュを行うとサウナ室内の湿度が上がるため一気に体感温度が高くなる。
サウナのスタッフが行うほか、
- オートロウリュ…マシンにより自動で行われるロウリュ
- セルフロウリュ…設置されている柄杓(ラドル)で自分で行うロウリュ
などがある。
アウフグース
サウナのスタッフがサウナストーブの上のサウナストーンにアロマ水などをかけて蒸気を発生させ、タオルを振って熱波を送るもの。
イベントとしてショー形式で演じられることもある。
羽衣(はごろも)
サウナから出て水風呂に入った際に、身体の周りにできる薄い水の層。
羽衣が出来ることで、水風呂の刺さるような冷たさを感じにくくなる。
「温度の羽衣」とも呼ばれる。
あまみ
サウナ・水風呂後に全身や手足にあらわれる赤い斑点のこと。
サウナの熱さと水風呂の冷たさの急激な温度変化により、血管が広がっているところと締まっているところがまばらに出てくることであらわれる。
サウナ飯
サウナ後の食事のこと。
ととのった後は味覚が敏感になるため、普段のご飯の何倍にも美味しく感じられる。(個人差有り)
さあ、サウナに行こう!
いかがでしたか?
サウナの世界はとっても奥が深いです。
全国各地の色々なサウナを訪れたり、サウナ飯を目当てにサウナを楽しんだりと、楽しみ方も人それぞれ。
まずはこの記事を参考にサウナの世界に足を踏み入れ、自由にサウナを楽しんでいただけたら嬉しいです。

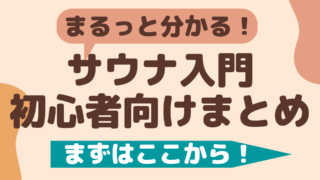
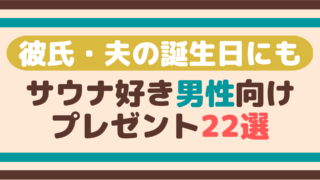


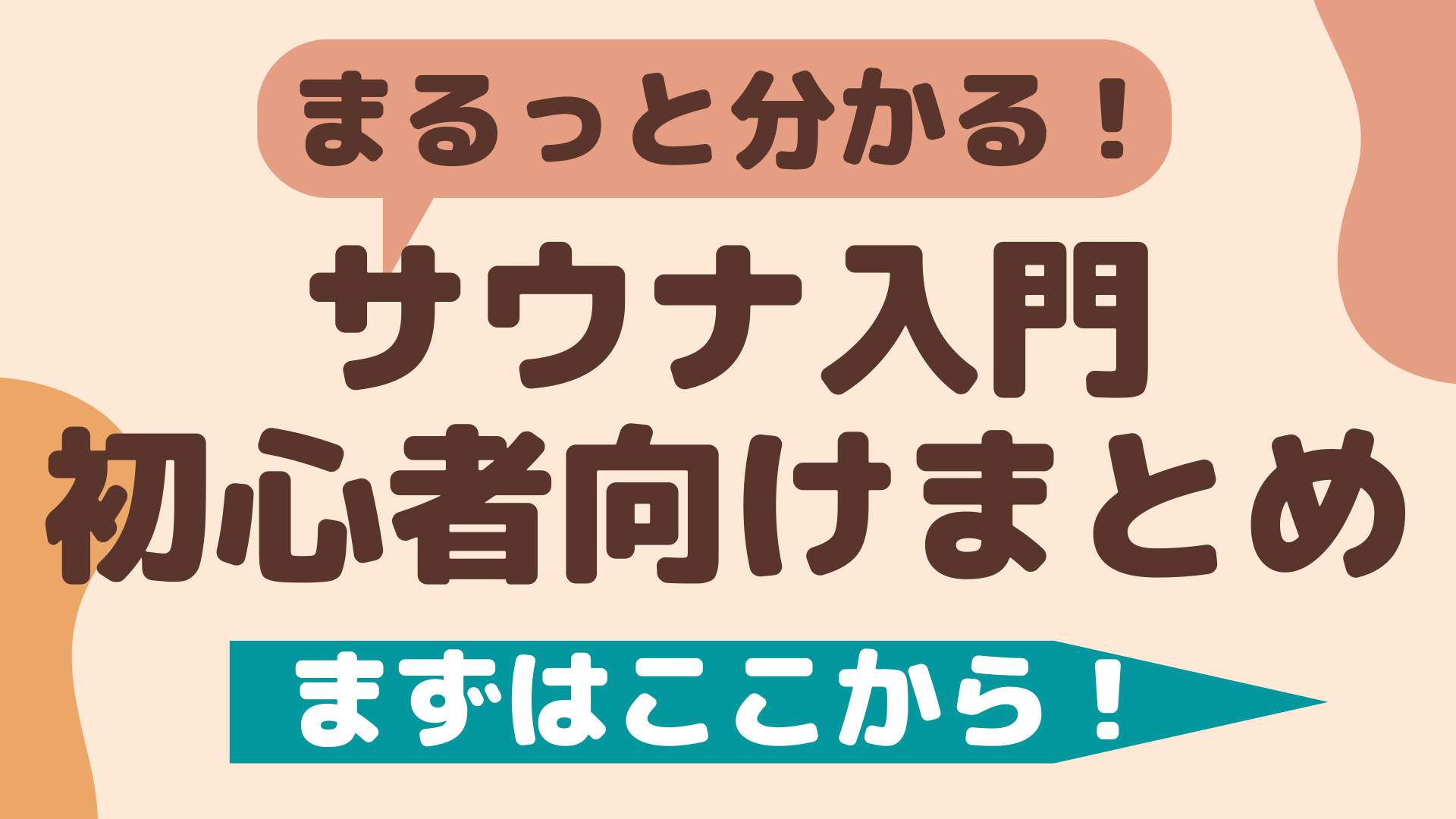
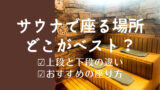
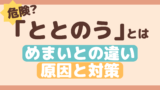
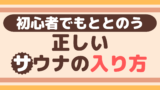
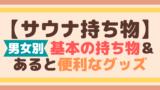
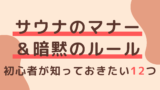
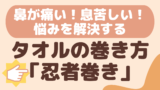

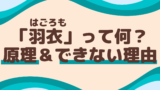
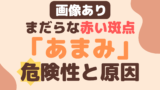
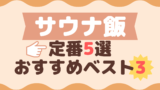
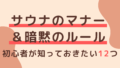
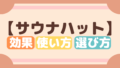
コメント